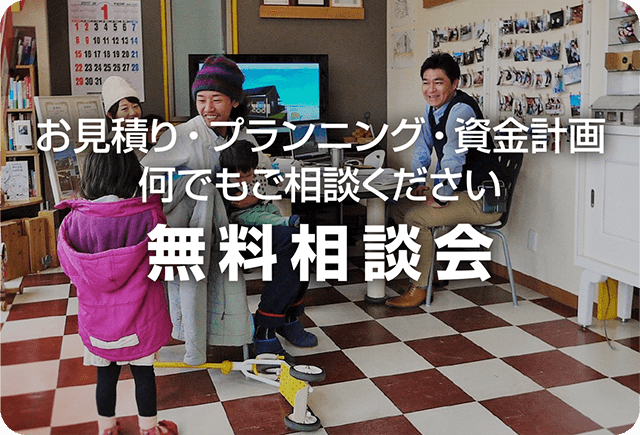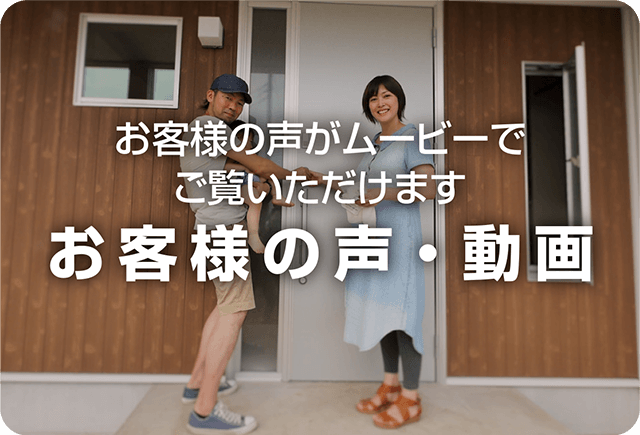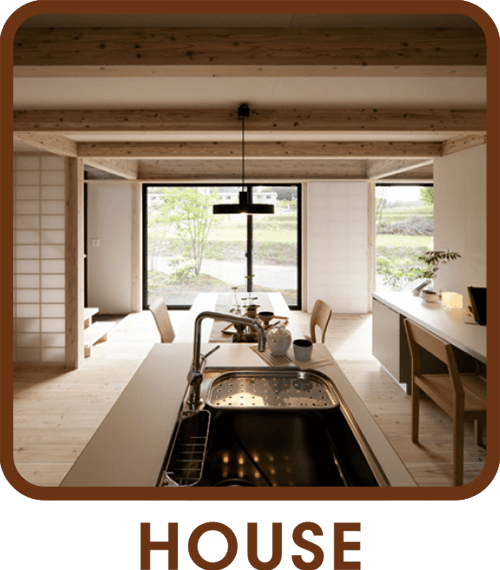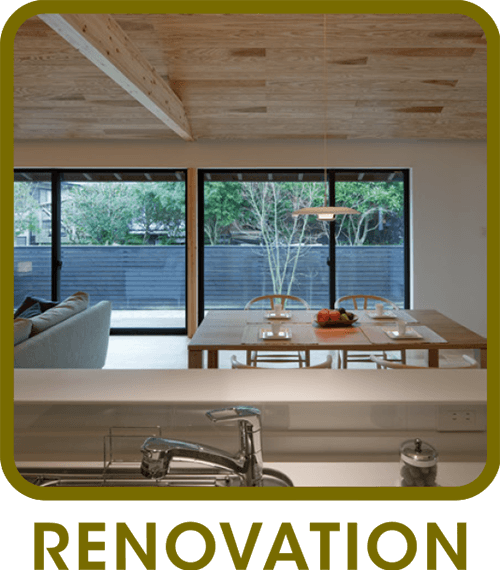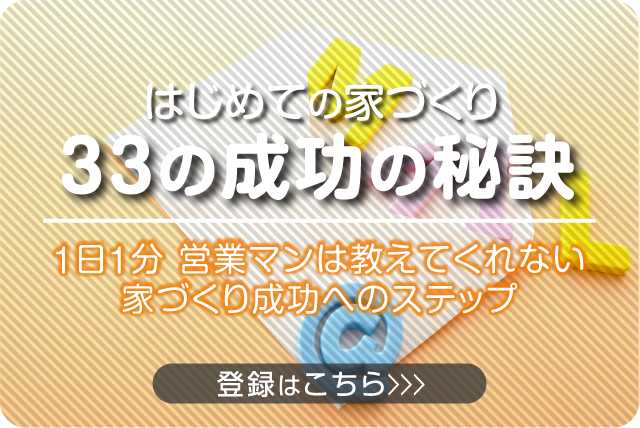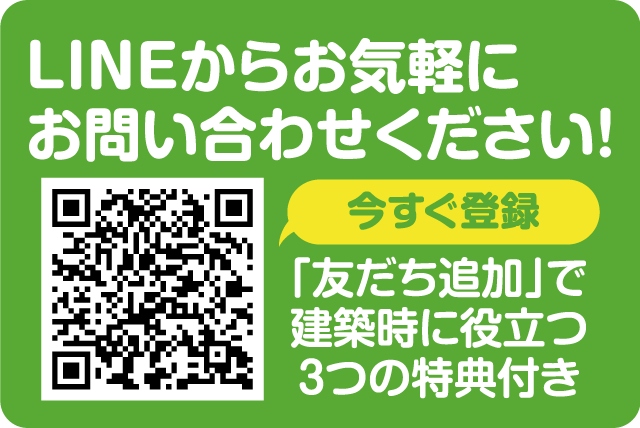高気密高断熱の家は乾燥するって本当!?
シンクホームの家は乾燥する!?
-冬の乾燥問題と対応策-
『室内干しの洗濯物がよく乾く』
シンクホームの家にお住まいの方からよく聞くお話の一つです。
とても良いことでもありますが、要するに【乾燥する】ということですね。
これは、高気密高断熱住宅には避けられない問題とも言えます。

[INDEX]
冬はなんで乾燥しやすいの?
そもそも冬になると乾燥するというのには、
【絶対湿度】と【相対湿度】という二つの要因が関係しています。
冬の乾燥の要因・【絶対湿度】との関係
【絶対湿度】とは…
実際に空気中に存在している水分量のことです。
日本の夏は高温多湿で、じめじめとしていますよね?
これは太平洋高気圧が関係し、非常に湿った空気が日本に流れてきます。
つまり【絶対湿度】が高い空気と言えます。
対して冬になるとどうなるかと言うと…
よく『西高東低の気圧配置』なんて聞くかと思いますが、
日本の北西、大陸側にシベリア寒気団と呼ばれる高気圧がみられます。
その高気圧からの風は、寒気を伴いとても乾燥しており、
それが日本海を渡って日本に流れてきます。
日本海上で海からの水蒸気をたっぷりと蓄えてきますが、日本の地形にもより、
上陸後に日本海側の山脈にぶつかって雨や雪に変わります。
雨や雪となり、含まれる水分の減った(絶対湿度の下がった)乾いた空気が、
その後山脈を超えて流れてくるという訳です。
(群馬で言う”赤城おろし”、”上州からっ風”ですね)
冬の空気が乾燥しているのは、西高東低の気圧配置と日本海側の山脈地形により、
絶対湿度が下がった状態になるから、ということですね。
冬の乾燥の要因・【相対湿度】との関係+おまけのお話
もう一つの要因である【相対湿度】との関係をお話します。
これは飽和水蒸気量のことでもあるのですが…
例えば、100㏄の水分が容量200㏄のグラスに入っているとします。
 100㏄の水分量が【絶対湿度】(実際に空気中に含まれる水分)
100㏄の水分量が【絶対湿度】(実際に空気中に含まれる水分)
容量200㏄のグラスが飽和水蒸気量
湿度で言うと50%となりますよね?
そして、このグラス(飽和水蒸気量)は温度が上がると大きくなります。

グラスが倍になって容量が400㏄になっても、
水分量である絶対湿度は100㏄のまま変わりません。
この状態は湿度が25%となります。
温度によって変化する飽和水蒸気量…
【相対湿度】とは、その変化に伴い相対的に変わる湿度のことを言います。
普段耳にする【湿度】とは、この【相対湿度】のことです。
そして、【相対湿度】がどう関係するかと言うと…
冬は寒いため、暖房器具を使いますよね?
暖房により室温(温度)が上がります。
しかし、そもそも【絶対湿度】の低い乾いた空気です。
室温の変化により、
より一層乾燥した(相対湿度の低い)空気になるということです。
■相対湿度のおまけのお話・結露のこと
飽和水蒸気量は温度によって変化する、という話でしたが、
温度が下がる、室温が低下すると、飽和水蒸気量は低下します。
先ほどの例えでいうグラスが小さくなるということですね。
そして、空気中に含まれる水分量がこのグラスの容量を超えるとどうなるかというと…
結露をしてしまうということです。
お家の結露というと窓が一般的です。
今はサッシやガラスの性能が向上していますが、
アパートや今までのつくりの家の窓は他と比べダントツに温度が低くなりますので、
その付近の飽和水蒸気量(水分の容量)の限界も低くなり、結露となります。
【高気密高断熱】高性能の家がより乾燥する理由とは?
乾燥のメカニズムについてはお分かりいただけたでしょうか?
気密性が良く断熱性能の良い家は、
室内であたためられた空気が外に逃げにくいため、
効率良く家全体をあたためることができます。
そのため、
【とても乾燥しやすくなる】ということです。
ここまでをまとめると…
①冬の空気には含まれる水分量が少ない。
②空気内に含むことのできる水分量は温度(室温)によって変化する。(飽和水蒸気量)
③高性能の家は室内であたためられた空気が外に逃げにくいため、効率良く家全体をあたためることができる。
④室温が上がると飽和水蒸気量は増える。
⑤水分量自体は変わらないため、相対的に湿度が下がる。
⑥乾燥する。
と、なります。
暖房器具による違いって?
ほとんどの方が、エアコンを暖房のために使用しているかと思います。
最も効率よく部屋をあたたかくする方法とは、やはりエアコンです。
しかし、
エアコンの暖房は室内の空気を取り入れて外に排出し、
室外の空気をあたためて室内へ放出します。
先ほどの乾燥のメカニズムの説明で分かる通り、乾燥とは空気の温度の変化により生じます。
空気を直接あたためるエアコンは、とても乾燥しやすいということです。
さらには、室内で加湿した空気も外に排出し、室外の乾いた空気を取り込みます。
加湿に対しても効率が悪く、乾燥のもう一つ要因と言えます。
では、どんな暖房器具が良いのかと言うと、【輻射熱】を利用したものです。
【輻射熱】とは?
電磁波によって熱を伝える方法で、物自体をあたためます。
ちなみにエアコンは【対流】、つまり気体の流れによって熱を運びます。
【対流】と【輻射熱】の違いで分かりやすい例えは、【直火】と【炭火】です。
【直火】は気体を通して熱を伝える【対流】であり、
お肉の表面はよく焼けますが、中までは火が通りづらい。
【炭火】は【輻射熱】です。
電磁波はお肉の深部まで届き、中までじんわりと火が通ります。
空気を介さずに、壁や床、身体自体をあたためてくれるので、
室温自体をそこまで高く上げなくても体感としてあたたかく感じやすいため、
エアコンに比べ乾燥はしづらいと言えます。
身近なもので『こたつ』、『電気ストーブ』、『石油ストーブ』…
他には『薪ストーブ』や、
昨年シンクホームの家でも導入いただきご好評いただいている『ペレットストーブ』、
すでに何人ものオーナー様に導入いただいている『蓄熱暖房機』があります。
『こたつ』や『電気ストーブ』は局所的なもののため、
それだけで部屋全体をまかなうのは難しいと言えます。
『石油ストーブ』については、燃焼により水や二酸化炭素が発生するため加湿にもなります。
高気密高断熱と呼ばれる以前のつくりの家やアパートなどで、そこまでの乾燥を感じづらかったのは『石油ストーブ』が主流として使われていたからとも言えます。
しかし、石油の燃焼により一酸化炭素など有害な物質も出ます。
高気密高断熱の住宅の場合、
換気については十分に気を付けないと危険な場合もありますのでご注意ください。
『石油ストーブ』と同じ燃焼させる暖房器具でも、
『薪ストーブ』と『ペレットストーブ』の場合は
排煙・排気のための配管があるため、換気の面では安全と言えます。
『蓄熱暖房機』も同様に安全と言えますが、
『薪ストーブ』『ペレットストーブ』『蓄熱暖房機』の3種は、
導入にも運転にもコストが掛かります。

乾燥を抑える方法と対策!
乾燥の要因について、ここまでお話をさせていただきました。
暖房器具の話も挙げさせていただきましたが、
高性能の家だからこそ、石油ストーブの利用が減り、
高効率なエアコンの利用が主流となったと言えます。
(今までのつくりの家は石油ストーブを使わざるを得なかったとも言えます。そして気密性の良い家に石油ストーブは不向きとなります。)
高性能の家と乾燥問題は切っても切れない関係と言えるでしょう。
ですので、しっかりとした対策が必要となってきます。
①サーキュレーターの活用
結露の予防にもなります。
シンクホームスタッフの家(casa amare)の2F北側の天窓もわずかですが結露します。
(リビングやランドリー、三角窓には結露なし)
なぜその窓だけ結露したのかと言うと、加湿した空気がそこに溜まってしまい、
さらに空気が冷えて飽和水蒸気量を超えてしまったため。
サーキュレーターでしっかりと空気の対流を作り、加湿した空気が一ヶ所に溜まらず、
全体に流れていけば、部屋全体、家全体の加湿へと繋がります。
ただ、冬に風が当たると寒く感じやすいので、設置場所には注意が必要です。
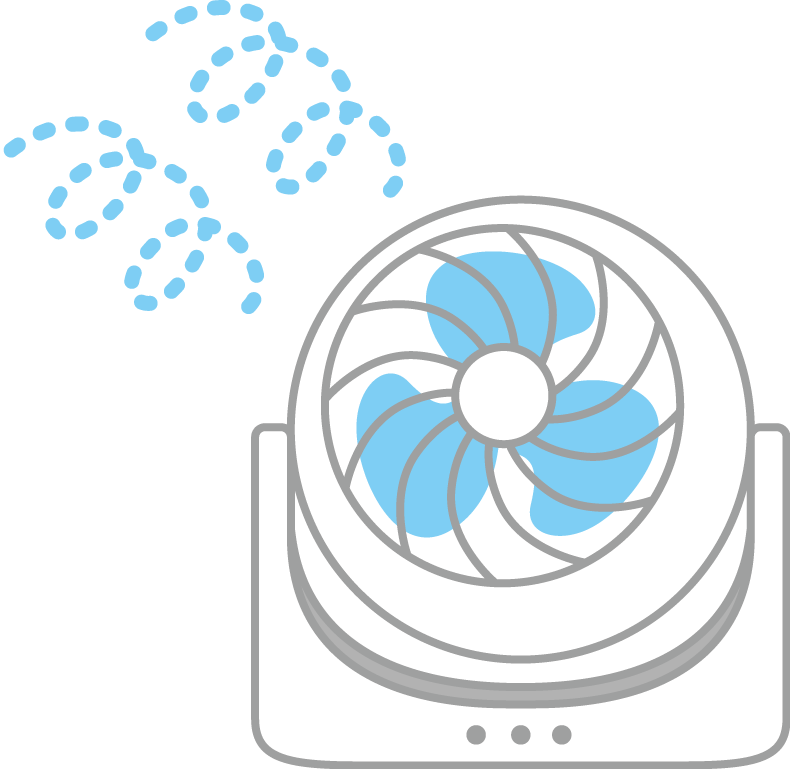
②適切な加湿量の加湿器を使用する
広い部屋にはそれに見合った加湿器が必要です。
高価にはなりますが、それなりのものを用意するのがベストと言えます。
ただ、加湿器を利用の際にはしっかりとメンテナンスにも気を付けてください。
加湿器は性質上カビの温床となりやすくなります。
『加湿器肺炎』なんていう病気もありますので、
フィルターやタンクなど、清潔に保つよう気を付けましょう。

③【輻射熱】を利用した暖房器具を使用する
エアコンはとても効率の良い暖房器具と言えますが、先ほどの説明の通り、
加湿した空気を外に排出し、室外の乾燥した空気を取り入れて放出しています。
【輻射熱】を利用した暖房器具であれば、エアコンよりも乾燥はしづらいと言えます。
ただ、導入にも運転にもコストは掛かります。
④とにかく室内干し
始めにもお話の出たとおり、シンクホームの家は洗濯物がとてもよく乾きます。
室内に干すことにより、湿度を上げることが可能ですので、
見た目はともかく、乾燥対策に室内干しをオススメと言えます。
室内干しに似た効果として、
お風呂に入ったあとのお湯をそのままにして、
ドアを開けたままにしておくという方法もあります。
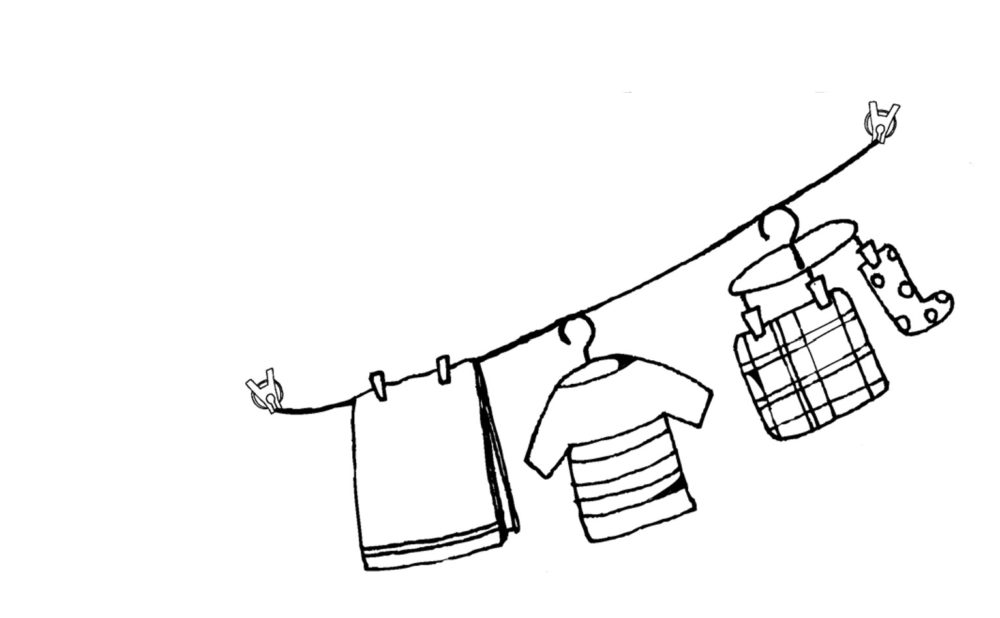
適切な対策で健康的な日々を!
いかがでしたでしょうか?
冷暖房効率の良い、
木や自然のぬくもりを感じられるシンクホームの家ですが、
高性能の家ほど、乾燥しやすいということが言えます。
乾燥するとウイルス感染の危険性も高まります。
室温を上げるのは意外と簡単と言えますが、
湿度を上げるのはなかなか難しい…
上手な乾燥対策をして、健康的で快適な暮らしを送りましょう!